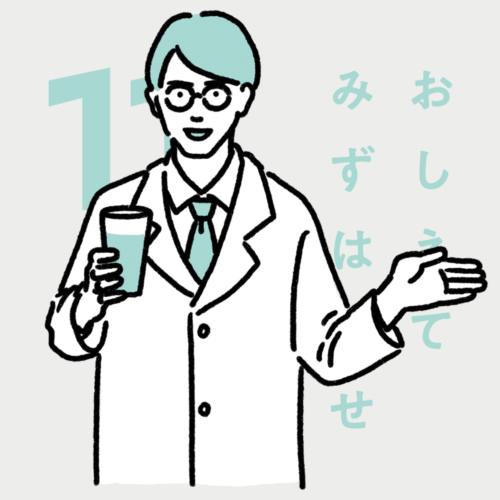水分補給におすすめ飲み物は?
目的に合わせてご紹介します
健康や美容のために水分補給を心がけている方は多いでしょう。体にとって水分補給が重要とわかってはいるものの、どのような飲み物を選べば良いのか飲むタイミングを悩んでいませんか。
この記事では、水分補給の必要性やおすすめの飲み物、水分を摂るタイミングについて解説します。
水分補給ってなんで必要なの?

私たちの体は、体重の約60%に相当する水分によりできており、普通の生活をしているだけでも約2.5Lの水分が汗や尿、皮膚・呼気からの蒸発などによって失われます。※1 水分補給をせずにいると体内の水分が不足し、脱水症状や熱中症になる可能性が高まるため注意が必要です。
脱水や熱中症のリスクを防ぐだけでなく、健康を維持するためにも水分補給は欠かせません。体内の水分のうち約3分の1は血液などの細胞外液として存在し、体のさまざまな組織に栄養や酸素を運ぶ役割を担っています。※2 体内の水分量が不足すると血中の水分も減少し、栄養や酸素をうまく運べず体調不良を引き起こしやすくなるのです。
また水には尿や便、汗などの老廃物を体外に排出する働きもあります。水分補給を怠ると、不要な老廃物が体内に蓄積されやすくなります。日頃から便秘に悩みがちな方は、水分不足が原因かもしれません。水分補給を心がけると便がやわらかくなり、排便がスムーズに促されるでしょう。※3
水分補給を習慣づけると健康な体を維持しやすくなるだけでなく、適切な体重管理もしやすくなります。水分補給の大切さについてより詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
水分補給の基本である水の種類
水分補給の基本となる水にはさまざまな種類があります。ここでは水道水、ミネラルウォーター、アルカリイオン(電解水素水)整水器、RO水、4種類の水について解説します。
水道水

水道水は、私たちが生活するなかで身近な水のひとつです。水道水の源水は地域によって異なるものの、ダム貯留水や河川水等の表流水がほとんど。※4 水源地の水は高度浄水処理によってカビ臭などが取り除かれた後、厳しい水質検査が行われて私たちの家庭に届けられます。※5
水質検査を通過するには厚生労働省が定めた水道法第4条の規定に基づき、51項目の水質基準に適合する必要があります。※6 日本の水道水は安全性と品質が保証されているだけでなく、ペットボトル入りのミネラルウォーターを購入する費用や手間を抑えられるのもメリット。ゴミが出ないため環境にも配慮できます。
クリンスイはそのような水道水に着目し、水にまつわる環境問題にも積極的に取り組むブランドです。また、ボトルを使わず水道水から浄水をつくる浄水器も豊富に展開しています。
浄水器には水の味を損なうカルキ臭を除去する機能があり、沸騰しただけでは取り除けない水道管のサビも除去できます。浄水フィルター内蔵のウォーターサーバーなら、冷水と温水を使えて便利です。
クリンスイの浄水器は家庭用蛇口に簡単に取り付けられます。水分補給にはもちろん、お料理にもおいしい水をたっぷり使えるように、さまざまな性能や機能の商品をラインナップしています。ウォーターサーバーは水道直結型でボトル交換は不要。オフィス用のウォーターサーバーをお探しの方にもおすすめです。
ミネラルウォーター
水分補給の飲み物として、水道水とミネラルウォーターのどちらにしようか迷う方もいるでしょう。水道水とミネラルウォーターは適用される法律や源水場所、処理方法がそれぞれ異なります。
ひとつ目の違いは、水道水の安全性は水道法によって確保されるのに対し、ミネラルウォーターには食品衛生法が適用される点です。※7 食品衛生法によってミネラルウォーターは「水のみを原料とする清涼飲料水」と規定されており、二酸化炭素を注入したもの(炭酸)やカルシウム等を添加したものも含まれます。
次に、水道水は厚生労働省が定めた水質基準項目と基準値があるのに対し、ミネラルウォーターは食品衛生法第13条に基づく「食品、添加物等の規格基準」によって安全性が確保されます。※7 除菌や殺菌工程の有無により区分けされ、さらに原水の採取場所や処理方法によって大きく4つに分類されるのです。
市販のミネラルウォーターは、特定の水源から採水された地下水(鉱泉水、鉱水など)を使用しているものがほとんどです。ミネラル分を人工的に調整したものや、飲用に適した水道水や河川の表流水を使用したものもあります。
処理方法も水道水とは異なります。ミネラルウォーターは原水を汲み上げた後、浮遊物を取り除くために沈殿やろ過の処理をし、加熱殺菌されるのが一般的です。
水道水とミネラルウォーターの具体的な違いは、こちらの記事もご覧ください。
アルカリイオン(電解水素水)整水器
水分補給をするための飲み物として、アルカリイオン(電解水素水)整水器を用いた水を選ぶのもおすすめです。
アルカリイオン(電解水素水)整水器は、浄水した水道水を電気分解し、アルカリイオン水(電解水素水)を生成する機器のことです。アルカリイオン水(電解水素水)は胃腸症状の改善に効果的と認められており、整水器は家庭用管理医療機器として認証されています。※8
クリンスイでは、ビルトインタイプのアルカリイオン(電解水素水)整水器をご用意しています。健康に気をつけながら水分補給をしたい方は検討してみてはいかがでしょうか。
アルカリイオン水(電解水素水)について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
RO水
RO水とは、水道水を逆浸透膜(RO膜)でろ過し、水分子以外の不純物をほぼ除去した水のことです。※9 別名「純水」や「ピュアウォーター」とも呼ばれます。ペットボトルに入れて販売されていたり、ウォーターサーバーの水に使用されていたりする他、医療や工業、食品加工などでも幅広く活用されています。
不要な物質が限りなく取り除かれているため、飲み物にはもちろん、小さなお子さまのいる家庭にもおすすめです。※9 料理に活用すれば、素材本来の風味をより引き立てられるでしょう。
目的別のおすすめ飲み物

水分補給の飲み物は、目的に合わせて選ぶことで効率的に水分不足を補えます。ここでは3つのシーンに分けて、それぞれにおすすめな飲み物の種類を紹介します。
日常的に摂取する場合
前述のとおり、人間の体は約60%が水分です。普通の生活でも尿や汗で水分は失われるため、こまめな水分補給を心がけましょう。
水分補給のタイミングは、喉が渇く前にするのがポイントです。喉が渇くのは脱水のサイン。特に高齢者の方は喉の渇きを感じにくく、脱水になりやすい傾向があるため注意が必要です。
健康な体を維持するのに必要な水分量は、1日2.5Lが目安です。しかし、1日2.5Lの水分を飲み物で摂取しなければならないわけではありません。私たちは毎日の食事から1Lの水分を摂取しているのに加え、体内で0.3Lの水が作られます。よって、飲み水として摂取する水分量は1日1.2Lとなります。※1
日常的な水分補給には、水がおすすめです。浄水器でろ過した水道水なら水質基準も高く、手軽においしい水を飲めます。コストも抑えられるため、毎日の水分補給にぴったりです。
味のない飲み物が苦手な方は、ノンカフェインの飲み物を選ぶとよいでしょう。カフェインの含まれていない麦茶やコーン茶、黒豆茶は、程よい甘みと香ばしい味わいが特徴です。体にも優しく、お子さまと一緒に飲むことができます。さっぱりとした口当たりが好みなら、ルイボスティーやハイビスカスティーもおすすめです。
水分補給におすすめの飲み物についてはこちらの記事も参考にしてください。
脱水症・熱中症を予防する場合
脱水や熱中症予防には、スポーツドリンクを選ぶとよいでしょう。水分と汗で失われた塩分を効率良く補給できるほか、ミネラルやブドウ糖など栄養分も含まれています。スポーツドリンクがない場合、水1Lに1〜2gの食塩を加えた食塩水を作って飲むと不足した塩分を補えます。※10
いざという場合に備えて、経口補水液を常備しておくと安心です。スポーツドリンクより塩分が多く含まれているため、脱水症状を起こした際の水分補給にも適しています。体液とほぼ同じ浸透圧で吸収速度が非常に高く「飲む点滴」とも呼ばれています。※11
脱水や熱中症の水分補給に糖分の含まれていない炭酸水もおすすめです。炭酸水を摂取すると血流速度が上昇し、熱が溜まった体を安静な状態に改善するといわれています。※12
スポーツをする場合
スポーツ中や前後の水分摂取には、スポーツドリンクがおすすめです。スポーツドリンクは水分補給だけでなく、エネルギー源となる糖質やビタミン、ミネラルを補うのにも良いでしょう。※13
糖質が含まれているものの、一般的な清涼飲料水の糖類が約10%の濃度であるのに対し、スポーツドリンクは約6~7%と低く抑えられています。※13 ただし多量に飲むと糖質を過剰に摂取することにもつながるため、適量を意識しましょう。
美容を意識する場合

美容を意識する方にとっても水分補給は欠かせません。体内の水分量が不足すると血液中の水分量も減り、血液がドロドロになります。すると皮膚の角質層がひび割れし、バリア機能が損なわれて肌荒れやかゆみを引き起こします。※14
また、水分不足はドライアイの原因のひとつです。体内の水分量が不足すると涙の量が減少し、目が乾きやすくなるといわれます。その結果、角膜に傷がついて目が疲れやすくなったり、炎症を起こして赤くなったりする可能性があります。※14
おすすめできない飲み物
水分補給は健康維持に欠かせません。一方、カフェインや糖分、アルコールを含む飲み物を摂取する際には注意が必要です。
カフェインが入っている
カフェインを含む飲み物には利尿作用があります。過剰に摂取するとかえって脱水を引き起こす可能性もあるため、水分補給には不向きといえるでしょう。人によっては下痢や吐き気を引き起こすこともあります。※15 胃腸の弱い方はなるべく控えて、カフェインを含まない飲み物を選びましょう。
カフェインが含まれる飲み物は、以下の通りです。
- コーヒー(インスタント含む)
- 紅茶
- 緑茶
- せん茶
- ウーロン茶
- エナジードリンク
- ココア
- コーラ
カフェインには利尿作用の他、心拍数の増加や高血圧のリスクを高める作用もあります。※15 適量であれば眠気覚ましになりますが、過剰に摂取すると不眠になる可能性もあるため注意が必要です。健康に不安のある方は水分補給の際、なるべくノンカフェインや水を選ぶのがおすすめです。
エナジードリンクは、コーヒーや茶類より多くのカフェインが含まれています。なかにはコーヒー2杯分に相当するカフェイン量を含むものも。飲み物だけでなく、サプリメントやガムなどにもカフェインは含まれています。日頃から気づかないうちに過剰に摂取している場合もあるため気をつける必要があります。
糖分が入っている
果汁や甘味料を加えた炭酸飲料や清涼飲料水(ソフトドリンク)、果汁入りジュースなど、糖分が含まれる飲み物も水分補給には向いていません。
糖分を含む飲料を多飲すると高血糖状態となります。血糖値が上昇すると喉が渇き、さらに水分を欲するといった悪循環が生まれます。重症化すると意識がもうろうとしたり、昏睡状態となる恐れもあるため注意が必要です。※13
ノンシュガーや微糖との表示がある飲料も気をつけたいところ。栄養成分表示には規定があり、ノンシュガーや微糖でも砂糖0gとは限りません。スポーツドリンクにも糖分は含まれています。清涼飲料水と同じく多飲には注意しましょう。
アルコールが入っている
アルコールはどれだけ飲んでも水分補給にはなりません。かえって体内の水分量が不足し、脱水症状が進むため注意が必要です。カフェインと同様、アルコールには利尿作用があります。たとえば、ビールを10本飲むと通常より尿の量が増えて、11本分の水分が排出されるといわれます。※1
アルコールを含む代表的な飲み物は、ビールやワイン、日本酒、ウィスキーなどです。寝酒としてアルコールを飲む方もいるでしょう。アルコールは寝つくまでの時間を短縮させる一方、睡眠障害を引き起こす原因にもなります。※16 利尿作用によって尿量が増えるため、夜間頻尿にもつながります。
就寝前の水分補給はもちろん、健康のためにもアルコールはなるべく控え、水やノンカフェインの飲み物を選ぶようにしましょう。
水分補給のタイミング

水分補給はタイミングも大切です。日常の水分補給は「喉が渇く前」と「入浴後・就寝時」を意識しましょう。その理由を以下で詳しく解説します。
喉が渇く前
水分不足による健康障害を防ぐには、喉の渇きを感じる前に水分を摂取するのが大切です。喉が渇いてから水分補給をする方法では脱水のリスクが高まるだけでなく、熱中症の原因にもつながります。
また、水分不足に対する感覚機能は年齢とともに衰える傾向があります。認知症や持病をお持ちの高齢者の方は、気づかないまま脱水状態に陥る可能性もあるため注意が必要です。※17 家族など周囲も協力しながら、こまめな水分補給ができるように見守ると安心でしょう。
入浴後・起床時
入浴をすると多量の汗をかき、水分が失われます。入浴後の水分補給はもちろん、できれば入浴前にもコップ1杯程度の水を飲んでおくとよいでしょう。
入浴中だけでなく、人間の体は就寝中にもたくさん汗をかいています。起床時に水分補給をすることで水分不足を防ぎ、健やかな体を維持しやすくなるでしょう。夏場はとくに就寝中の発汗量が多くなり、普段に比べて起床時に脱水状態に陥りやすいです。※18 熱中症のリスクも高まるため、いつも以上に水分補給を意識しましょう。
水分補給におすすめな飲み物は水

日常的な水分補給には、水がおすすめです。脱水や熱中症、スポーツで多量の汗をかく場合はスポーツドリンクを活用し、上手に水分不足を補いましょう。
外出時の飲み物は、水や自家製の食塩水をマイボトルに入れて持参すればコストを節約できます。使い捨てペットボトルのごみや輸送時のCO2を9割以上削減できるので、環境に優しい取り組みの小さな一歩にもつながります。ぜひクリンスイの浄水器を使って、おいしいお水を外出先でも楽しんでくださいね。
三重・多気町の商業リゾート施設VISON(ヴィソン)の一角にある「クリンスイハウス」では、クリンスイのおいしい水を無料で試飲できます。ビルトインタイプの蛇口一体型浄水器も体験可能。
身近な水道水で水分補給を手軽においしく楽しみたい方は、以下のページを参考に自分にぴったりな浄水器を見つけてください。
関連商品
【参考文献】
※2 千葉県営水道|その12体内の水の働きと水を飲むことについて
※4 公益社団法人日本水道協会|水道資料室:日本の水道の現状
※5 公益社団法人日本水道協会|安全で美味しい水道水供給の推進
※8 独立行政法人医薬品医療機器総合機構|医療機器等基準関連情報
※9 浄水器協会|逆浸透膜浄水器|RO浄水器ってどんなもの?
※11 農林水産省|消費者の部屋|熱中症対策には、水よりスポーツドリンクを飲むとよいと聞いたのですがどうしてですか。また、経口補水液との違いも教えてください。
※13 厚生労働省|e-ヘルスネット|嗜好飲料(アルコール飲料を除く)

谷口 英喜
日本麻酔科学会を始め、多数の学会で専門医・指導医を務める麻酔医師・医学博士。神奈川県済生会横浜市東部病院患者支援センター長も務める。栄養分野も専門としており、脱水症に対する治療法「経口補水液療法」の第一人者としても知られている。『いのちを守る水分補給: 熱中症・脱水症はこうして防ぐ』を始めとした著書も多数。